【製造業の改善と革新の会】
木曜メールマガジン
”原理からのDX”を語る
元トヨタ業務改革室長
#015
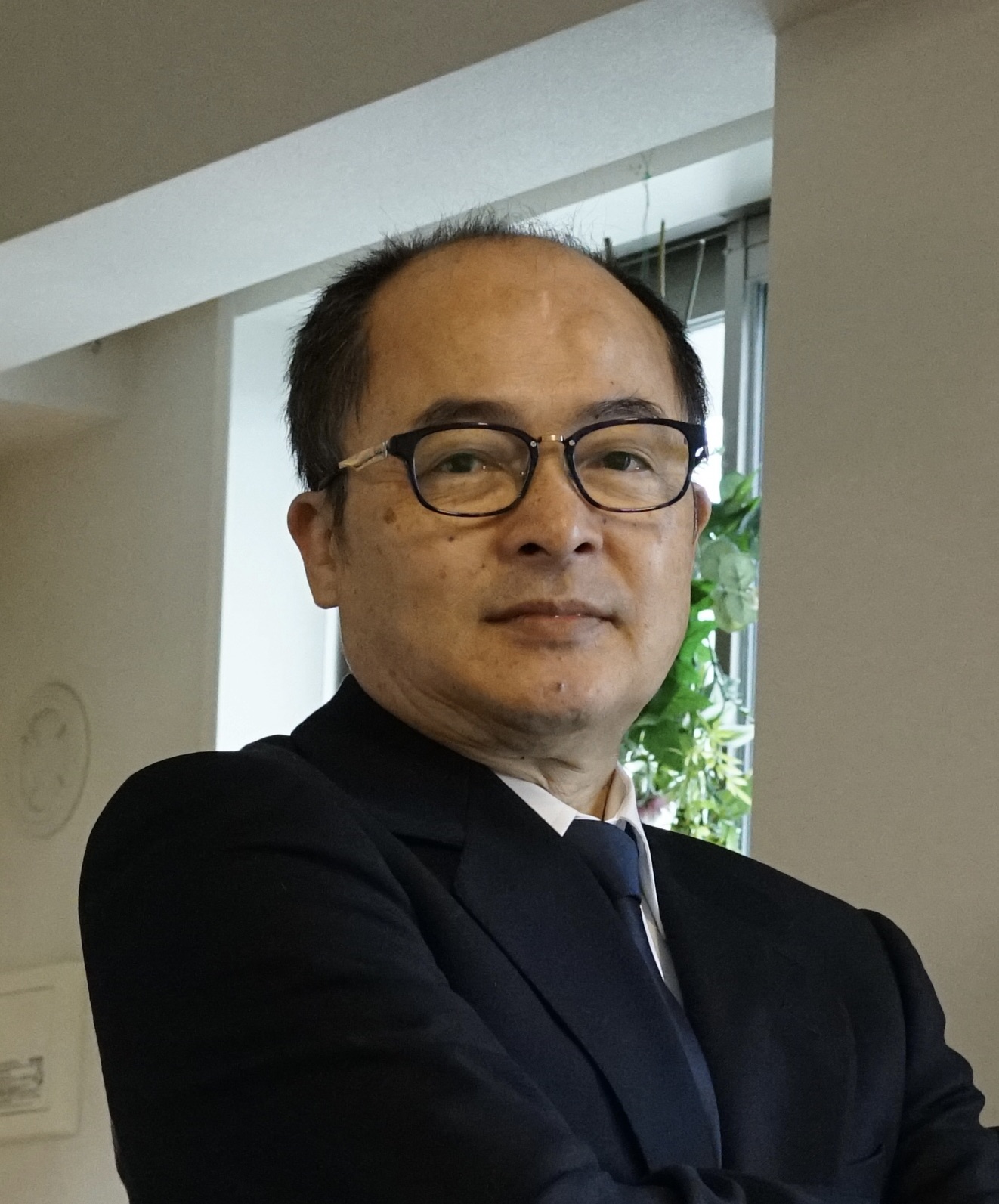
3月からのテーマ
【製造業のDX推進】
製造業でのDXはなかなか難しいと思いませんか?IT化と革新は全く違う言葉であるのに、一体と解釈させている論調が問題ですね。
今後の配信予定
7、DXリテラシイとは 次回以降
【2、革新を生む思考法とは】
1、はじめに
DXの記事や講演を聞くと、その推進のためにIT知識の習得に力点がより過ぎているように思えてなりません。革新を企業に生み出すにはどのよう思考が必要なのかを考えてみたい。
昔の糸川英夫さんの”未来を開く着想”には当時から新しい視点が展開されています。
実は、私は約50年前の時代の書籍から考える方法についてを好んで読んでいます。
例えば、川喜田二郎著の”発想法”、梅澤忠雄著の”知的生産の技術”、40年前の竹内均著の”哲学的思考のすすめ”、20年前の立花隆著の”思考の技術”、野中郁次郎著の”知識経営のすすめ”、松岡正綱著の”知の編集工学”など。近年10年前後にはデザイン思考などの欧米の著者による書籍が多く出版されていますが、どうも腑に落ちません。
そんな訳で、今度は日本文化や言語など日本人気質についての書籍を読みながら、欧米人と日本人の本質的な違いを理解しようと学んでいる最中です。
なぜ、このようなことを最初にお話をするのかといえば、戦後、日本の中には欧米のマネもあったと思いますが、独自の製品も多く創造し、海外に輸出しています。最近の新聞などの共通した論調は、低下した日本の製造業とか、周回おくれのIT利用など、本当にそうなんだろうかとの疑問を持つ文脈が多くあります。
日本ほど、多くの固有技術と芸能や工芸品、そして創造のための多くの道具とその技法を伝承する師弟関係がある国はないのではないでしょうか?
企業の規模が個人など小さな形であることが多いのですが、それはもっと大企業化すべきなのでしょうか?
人が生産性高く、想像力を発揮して創造できるには、多くの社員が必要なのではなく、真理を追求できる考える力を身につけた人材が数名いるだけで十分なことではないかと思います。そのくらいに、革新を生むことのできる人は少ないのです。
すると、重要なことは、革新を生める人材をどのように育てるかにあるということです。
糸川英夫さんの未来を開く着想には組織工学について述べられ、組織工学とはシステム工学、システム・エンジニアリングの一つとして述べられています。
そしてこれはコンピュータのプログラマーだけではなく、数学を優先する学問など多くの解釈によって用いられている言葉であると書かれています。
それらを組織工学と読んで研究を行い、日本が技術導入型から技術開発型に転換するにはどうするかという問いの答えを求め続けていたのです。
作る製品に合った組織を作ることが日本は下手だとも述べています。今日のシステムエンジニアということの起源はこのようなことであり、組織のあり方をプロセスも含めて考えることのできる人をシステムエンジニアと呼ぶべきではないでしょうか。
2、革新を生む思考法とは
糸川先生の書籍の中で、
①考えられるだけの要素、知識、情報を並び立てること
②要素、知識、情報の可能なあらゆる組み合わせをつくること
③できた組み合わせに採点、評価を与えること
④この中から最優秀なものを1つか2つを選択すること
とあります。ここで全ての組み合わせと評価となるともはやコンピュータの力を借りるしかありません。
近年、コンピュータの性能が格段に向上したことで、この処理も行えるようになったと思います。
ただ、重大なポイントは評価の内容についてです。コンピュータが評価方法まで生成することはできません。ビジネスの中で、評価指標は変化していくものです。そして、変化することで、環境に対応できていくことができます。ここには人間が考えることが必要な分野があります。
更に、①についてもどんな範囲について考えを整理するかという点についても、人間が考える必要があります。この考える範囲が組織や会社の中では個人としてもまちまちです。この範囲を制約をかけることはできないのです。人の自由な思考を妨げることになるからです。
革新を生む思考をする人は、他とは異なる思考ができることにより、価値ある変化の視点に気づくことができるからです。
しかし、その変化の視点を会社の中では共有する必要があるため、共有する整理対象の範囲を前提として、考えた要素や情報から、革新するための理由(要因)と対策方向をストーリー立てて説明することになります。
一般的にコミュニケーションが取れないとか腑に落ちないとの言い方は、もっと論理的に説明して欲しいという欲求です。
実際に人の心に伝わるストーリーを作るのは大変です。一旦、そのストーリーの信者に招き入れてしまえば、その力は何倍もの影響力をもって展開できることになります。
このような思考や整理の方法が企画の立案というものになると思います。
企画を立案したことの無い人にとっては、そもそもその方法から学ぶ必要があります。学校でもそのような方法を教えていないと思います。学校では学ぶ方法を教えてくれません。
ですから、特にものづくりにおける新製品、業務革新の企画を行う思考法などは属人的で行われているものです。
DXというX(トランスフォーメーション)を考えることが重要で、その次に、デジタル的な発想を用いて業務を抽象化することが必要です。
業務を抽象化せずに、具体的な業務のまま問題を定義するのでは、その具体的な業務だけが解決されず、ちっぽけな進歩に留まってしますからです。
この抽象化ステップを行わずして、目の前にある欧米のシステムツールにfi to standard しても日本の生産性は低下するばかりだと思います。
日本流のシステムを構築すべきで、それを展開していくことがDXとしては正しいのでは無いでしょうか?
業務プロセスを何の目的で変化させる必要がなぜあるのかに焦点を当てて、ブレない目的思考を行うことが必要です。
それができるシステムエンジニアを経営者は探しているのでは無いかと思います。つまりそれが組織工学を行うエンジニアの仕事だと思います。
次回のテーマ
【DXと製造業】
最後まで購読いただきましてありがとうございます。
次回は、IT業と製造業の本質的な違いをお話しします。
ご興味のある方は、下記のボタンからメールマガジンの購読登録をお願いいたします。最新で製造業の考え方についての情報をご提供いたします。一度だけ登録いただければ解除するまで配信されます。また、購読解除はいつでも行えます。